病気不安症とは?治った体験談をご紹介! 症状や原因、治療法についても解説!

体調の小さな変化が気になったり、「何か重大な病気かもしれない」と不安に駆られたりするのは、多くの方が一度は経験することかもしれません。
しかし、その不安があまりにも強い場合は、“病気不安症”とよばれる疾患を発症している可能性があります。
本記事を通して、病気不安症の症状や原因について正しく理解し、不安を乗り越える第一歩を踏み出しましょう。
NPO法人生活の発見会は、医療機関でないため、薬を使わず根本的に神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)に対処する「森田療法」が学習できる自助組織です。
全国120の森田療法協力医と連携し、神経症でお悩みの方を支援しています。
以下動画では、森田療法について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
NPO法人生活の発見会では、「森田療法」を学び、神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)を乗り越えた人達が中心となり「森田療法」を学び合える集談会を開催しています。
集談会では、同じ悩みを持った人達の話が聞けるため”自分の苦しみを共有”することができます。また、神経症を克服した人の話も聞けるので、症状克服への知恵と力がもらえます。
集談会に参加することで、神経症克服の第一歩となるでしょう。
予約なく参加も可能ですので、ぜひお近くの集談会に「お試し参加」してみてください。
病気不安症とは?

病気不安症とは、「自分は重い病気にかかっている」あるいは「これから発症するのではないか」と強く思い込む精神疾患です。
実際には身体的な症状がみられない、または軽度であるにもかかわらず、患者本人は罹患の可能性に強くとらわれ、不安を感じつづけます。
病気不安症の診断では、身体的な症状そのものの有無よりも、健康に対する過度な不安やそれに伴う心理的・行動的反応に焦点が当てられます。
和田秀樹先生のYouTubeチャンネルで「生活の発見会」が取り上げられました。
病気不安症の特徴
病気不安症は、健康に対する強い不安にくわえて、身体的な症状が現れることもあるのが特徴です。
とはいえ、これらの症状は軽度であることが多く、診察や検査を行っても、患者が懸念しているような重大な疾患は確認されないケースがほとんどです。
病気不安症にみられる主な症状

では、病気不安症を発症すると、具体的にどのような症状がみられるのでしょうか。
精神面・身体面それぞれの主な症状を、以下でお伝えします。
【精神的な症状】
・「自分はなんらかの病気ではないか」と思い込む
・「なんらかの病気にかかりそうだ」と不安になる
・「命を脅かすような重大な病気にかかっているに違いない」と信じ込む
【精神的な症状】
・ 倦怠感
・吐き気
・嘔吐
・動悸
・胸痛
・胃痛
・発熱
・脈の乱れ
・耳鳴り
仮に身体的な症状が現れたとしても軽度にとどまることが多いわけですが、患者はそれを重篤な疾患だと受け取り、やがて強い恐怖心へと発展していきます。
病気不安症を引き起こす原因
病気不安症を発症する原因は、まだ解明されていません。
しかし、過去に重篤な病気にかかったことや、身近な人の病気を目の当たりにしたことなどが発症の一因になるのではないかと考えられています。
また、幼少期に虐待を受けた方や、命に関わるようなトラウマ体験をした方も病気不安症を発症しやすいとされています。
病気不安症の診断基準
病気不安症かどうかを判断する際は、以下の診断基準に基づいて医師による慎重な評価が行われます。
【病気不安症の診断基準の例】
- 病気にかかりつつある、あるいは重い病気にかかっていると思い込んでいる
- 身体的な症状がない、または症状があっても軽度である
- 健康状態への強い不安がある
- 健康状態を過度に確認する、あるいは受診を拒む
- 病気に関する不安が6か月以上続いている
- これらの症状が、うつ病やパニック症といったほかの精神疾患では説明できない
病気不安症の診断でまず行われるのは、実際に病気にかかっていないかどうかを確かめるための診察や検査です。
そのうえで医師が、「病気にかかっていない」あるいは「軽度である」と本人に説明しても、病気に対する強い不安が6か月以上続く場合に、病気不安症と診断されます。
関連記事:うつ病とパニック障害は併発する?関係性や治療方法も解説
病気不安症を発症することによって起こる影響
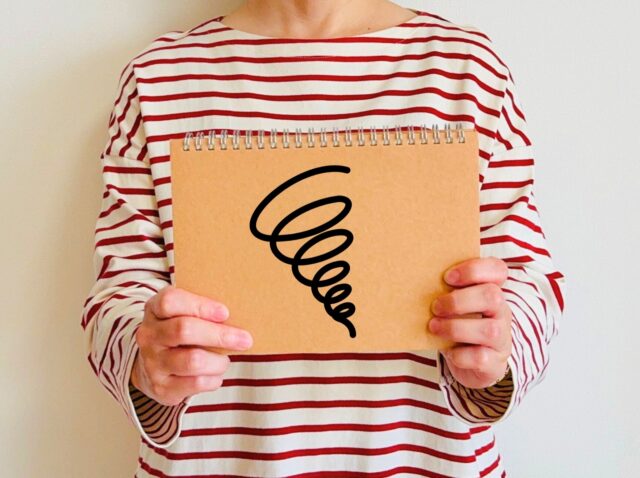
ここからは、病気不安症の発症が日常生活に与える影響をお伝えします。
以下の内容を、順番に見ていきましょう。
【病気不安症を発症することによって起こる影響】
- 医療機関を何度も受診してしまう
- 正確な診断までに時間がかかる可能性がある
- 周囲への不信感につながる
医療機関を何度も受診してしまう
病気不安症を発症すると、「重い病気にかかっているのではないか」という強い思い込みから、必要以上に医療機関を訪れ、検査を繰り返し受けてしまうことがあります。
検査で異常が見つからなかったとしても、健康に対する不安は消えず、医療機関を受診しつづけるため、通院に多くの時間や労力を費やすことになります。
これにより、仕事を休まざるを得なくなったり、家庭での役割をこなせなくなったりと、人間関係や日常生活に影響が及ぶケースも少なくありません。
正確な診断までに時間がかかる可能性がある
正確な診断にたどり着くまでに時間を要する点も、病気不安症を発症することで起こる影響の一つです。
病気不安症では、「なんとなく不安」や「だるい」といった、抽象的な症状が現れるケースも珍しくありません。
そのため、あらゆる病気の可能性を考慮して幅広い検査を受けることになり、病気不安症と診断されてから適切な治療を開始するまでに時間がかかってしまいます。
周囲への不信感につながる
病気不安症の発症により、自身の不安を真剣に受け止めてもらえない経験が続くと、周囲への不信感につながる可能性もあります。
患者本人は強い不安や心配を抱えていても、それが症状としてなかなか表に出ないため、周囲に気持ちを理解してもらうことは難しいものです。
こうした日々が続くと、孤立感を抱き、徐々に人との交流を避けるようになります。
病気不安症の改善方法

病気不安症の改善方法には、精神療法と薬物療法の2つが挙げられます。
これらは症状の程度や患者の状態に応じて単独で行われることもありますが、多くの場合、組み合わせて実施されます。
主な精神療法としてまず挙げられるのは、“森田療法”です。
森田療法とは、自分自身のなかにある感情を“あるがまま”に受け入れながら、行動を立て直し、生活全体を充実させていく療法です。
この療法を継続的に実践して、自身の本来の性格を活かすことで、不安や恐怖心に対する心の変化がみられていくと考えられています。森田療法は自助組織「生活の発見会」で学ぶことができます。
また“認知行動療法”も、病気不安症の改善方法として知られる精神療法の一つです。
認知行動療法では、“軽い症状=重い病気”と結びつける思考を見直し、過剰な健康確認や回避行動を減らす方法を学びます。
行動実験を用いた実践的なアプローチを通じて、不安を客観的に扱うスキルを養うことが、この療法の主な目的です。
薬物療法としては、抗うつ薬の一種である“選択的セロトニン再取り込み阻害薬”を服用する方法があります。
この薬には、過剰な不安や心配を和らげる効果があるとされています。
なお、ここで紹介した精神療法や薬物療法は、患者一人ひとりの考え方や症状によって相性が異なるため、治療の際は医師と相談のうえ、自身に合った方法を選ぶことが重要です。
関連記事:森田療法とは?自分で実践できる?森田療法のやり方や「あるがまま」の姿勢について解説!
病気不安症の治療期間
病気不安症の治療期間は、症状の程度や治療のスタイルなどによって異なりますが、精神療法で数か月程度、薬物療法で数か月~1年以上かかるといわれています。
改善のスピードには個人差があり、短期間で効果を感じる方もいれば、長期的な治療が必要になる方もいるため、自身のペースで焦らずに取り組むことが大切です。
治療期間が長くなったとしても自身を責めるのではなく、少しずつ努力を積み重ねることで、充実した日常生活を取り戻していきましょう。
病気不安症の改善に向けて自身ができること
病気不安症の改善には、信頼できる医師のもとで継続的に治療に取り組むことが肝要です。
特に、複数の医療機関を転々とする“ドクターショッピング”は、医師ごとに異なる見解に触れることで不安が増幅し、かえって症状を悪化させるリスクがあります。
こうした負の連鎖を防ぐためにも、まずは安心して相談できる医師と信頼関係を築き、治療方針をじっくり話し合うことが改善への第一歩です。
病気不安症が治ったという方の体験談
以下では、病気不安症の治療方法のうち、森田療法に取り組んで病気不安症と向き合う方法を学んだ方の声をご紹介します。
治療を検討する際の参考となれば幸いです。
森田療法を学び、不安症(全般性不安障害)・トイレ不安~とらわれからの回復 (Y・A、女性、会社員)
森田療法は、不安症(全般性不安障害)によるトイレ不安に悩んでいたY.Aさんにとって、心のよりどころとなっていたそうです。
Y.Aさんは、過去の出来事がトラウマとなってトイレ不安にとらわれる日々が続き、次第に生活範囲が狭くなっていました。
そのようなときに森田療法に出会い、「この苦しさからすぐに解放されたい」という思いから生活の発見会への入会を決めたと言います。
集談会に参加し、森田療法について学習するなかで、ご自身でも気づかぬうちに症状が緩和したことを実感されています。
|
強迫性障害(強迫症)~雑念恐怖、疾病恐怖、昇格恐怖を森田療法で克服
こちらの方は大学受験時に強迫性障害を発症し、雑念をはじめ、さまざまな恐怖を抱くようになりました。
こうした恐怖から精神科の受診を考えていたところ、生活の発見会の初代理事長である長谷川洋三氏の著書『行動が性格を変える』に出会い、森田療法を知ったそうです。
その後、生活の発見会に入会し、ゼロから森田療法を学んでいきました。
恐怖に襲われて落ち込む日もあったそうですが、やるべきことを一つひとつ丁寧にこなしていくうちに、症状を忘れる時間が長くなったと語っています。
|
病気不安症とは、健康状態に対して強い不安を抱く精神疾患

病気不安症とは、実際には病気にかかっていない、あるいはごく軽度であるにもかかわらず、重い病気にかかっていると強く心配しつづける精神疾患です。
本記事をご覧いただき、もしも「病気不安症かもしれない……」と感じたら、自己判断で医療機関を転々とせず、信頼できる医師のもとで継続的に治療に取り組むことが大切です。
不安の悪循環を断ち切り、焦らずに自身のペースで少しずつ心身の安定を目指しましょう。
森田療法にご興味のある方は、自助グループ・NPO法人である「生活の発見会」までご相談ください。
病気不安症をはじめとする神経症を克服した方々と共に、森田療法を学ぶ集談会を開催しています。
