広場恐怖症とは?発症の原因や診断方法を解説

特定の状況に対して、大きな恐怖心や不安感を抱いていませんか?
それは、もしかすると広場恐怖症とよばれる状態かもしれません。
広場恐怖症は適切に対処すれば改善できるため、ご自身に合う方法を知ることが大切です。
本記事では、広場恐怖症について、特徴や対処方法など基本的な情報をお伝えします。
ご自身の不安や恐怖の正体を知り、安心して毎日を過ごせるようになりたい方はご一読ください。
NPO法人生活の発見会は、医療機関でないため、薬を使わず根本的に神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)に対処する「森田療法」が学習できる自助組織です。
全国120の森田療法協力医と連携し、神経症でお悩みの方を支援しています。
以下動画では、森田療法について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
NPO法人生活の発見会では、「森田療法」を学び、神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)を乗り越えた人達が中心となり「森田療法」を学び合える集談会を開催しています。
集談会では、同じ悩みを持った人達の話が聞けるため”自分の苦しみを共有”することができます。また、神経症を克服した人の話も聞けるので、症状克服への知恵と力がもらえます。
集談会に参加することで、神経症克服の第一歩となるでしょう。
予約なく参加も可能ですので、ぜひお近くの集談会に「お試し参加」してみてください。
広場恐怖症とは

広場恐怖症は、不安症の一種で、すぐに逃げられない場所や、助けが得られそうにない状況あるいは場所にいることに強い恐怖や不安を抱く状態を指します。
“広場”とはつくものの、不安の対象は広場に限りません。
たとえば映画館やバス・電車の中など、恐怖から逃げられず安心できない場所に恐怖を感じる場合も、広場恐怖症に該当することがあります。
このような状況でパニックが起きたときに「逃げられないかもしれない」「誰にも助けてもらえないかもしれない」という気持ちになってしまうのです。
結果、同じような状況になるのを回避する、あるいは誰かの付き添いがなければ行けない、といった状態になります。
なお、広場恐怖症は2012年まで、パニック障害の重症化を示すひとつの症状として考えられていました。
その後2013年に、独立した一つの疾患として初めて認識されるようになったため、広場恐怖症そのものを対象とした研究や論文の数はまだ不十分なのが現状です。
和田秀樹先生のYouTubeチャンネルで「生活の発見会」が取り上げられました。
広場恐怖症の発症率

アメリカの精神医学会が発行している、精神疾患の診断・統計マニュアルである『DSM-5』(2013年)には、広場恐怖症の発症率が記載されています。
DSM-5によると、これが発表された2013年時点で青年・成人の約1.7%が毎年、広場恐怖症として診断されているのだそうです。
そして発症年齢の平均は17歳で、全症例の2/3は35歳前で初発しているとされています。
前述の通り、2025年時点で広場恐怖症は一つの疾患として扱われるようになってからまだ10年程度しか経っていません。
今後より多くのデータが集まることで、発症率などの数値も変化していく可能性があります。
広場恐怖症の原因
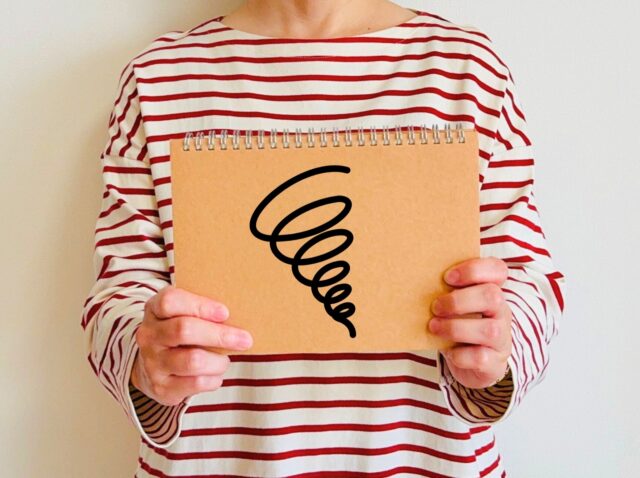
広場恐怖症を発症する原因には、大きく分けて“遺伝的要因”“心理社会的要因”の2つが挙げられます。
広場恐怖症になりやすい遺伝的素因の影響が、一部の研究で示唆されています。
ただし、親に広場恐怖症があるからといって必ずしも子どもも発症するわけではありません。
あくまでも傾向の一つであるとお考えください。
また心理社会的要因とは、特定の疾患の発症につながる環境や体験のことです。
広場恐怖症においては以下のような体験が関係しているとされています。
【広場恐怖症となり得る心理社会的要因の一部】
- 虐待や体罰、ネグレクト、経済的困難などの、小児期の逆境的な体験
- 過保護・優しさの欠如・権威主義などの生育環境
- 離婚やパートナーの死去、別居
さらに、家庭や友人関係、仕事などによるストレスが症状を悪化させる可能性もあります。
広場恐怖症に似た病気

広場恐怖症とよく似た症状が現れる精神疾患としては、以下の3つが挙げられます。
【広場恐怖症に似た病気】
- パニック障害
- 社交不安障害
- 特定のものに対する恐怖症
なお、これらの病気は広場恐怖症に似ているだけでなく、合併することが多い病気でもあります。
また広場恐怖症も以下の精神疾患も、基本的には“不安障害”とよばれるものの一部であり、後述する適切なケアによって管理が可能です。
パニック障害
パニック障害は、動悸や息苦しさなどの身体的な症状と「このまま死んでしまうのではないか」という大きな恐怖が、突然訪れる病気です。
以前は「パニック障害の二次的な疾患が広場恐怖症だ」と考えられていました。
しかし、2013年にアメリカの精神医学会によるガイドライン『DSM-5』で広場恐怖症が独立した疾患として扱われるようになったことにより、現在はそれぞれ異なる疾患とされています。
広場恐怖症とパニック障害の大きな違いは、症状の発生条件です。
広場恐怖症は、特定の状況や場所に置かれると強い恐怖を感じるのに対し、パニック障害の症状は何の前触れもなく突然起こります。
関連記事:パニック障害(パニック症)とは?治った体験談をご紹介!症状や原因、治療法についても解説!
社交不安障害
人から見られる状況や、初対面の人と接する状況など、社交的な場面に対して大きな恐怖や不安を感じる精神疾患が、社交不安障害です。
「自分は何かおかしいことをしていないか」「相手の迷惑にならないか」といった不安が大きくなり、身体的な症状につながります。
具体的な症状としては手足の震えや動悸などがあり、上述のパニック障害と似ている点が特徴です。
また、苦手な状況を避ける“回避行動”とよばれる行動がみられることもあり、これによって学校や仕事に行けなくなる場合もあります。
広場恐怖症では特定の場所に対して恐怖を抱きますが、社交不安障害は「こう思われたらどうしよう」という相手からの評価への恐怖がトリガーとなる点が大きな違いです。
特定のものに対する恐怖症
上記以外にも、特定の対象へ過度な恐怖や不安を抱く恐怖症も、広場恐怖症と似ています。
恐怖を抱く対象には、たとえば以下のようなものが挙げられます。
なお、以下はあくまでも一例です。
【恐怖症の対象となるものの一例】
- 高いところ
- 動物
- 昆虫
- 雷雨
- 注射
- 血液や傷
このように特定のものに対して起きる恐怖症は、限局性恐怖症ともよばれます。
具体的な症状としては、特定の状況を避ける回避行動がみられるほか、手足の震えや動悸をはじめとするパニック発作を引き起こすこともあります。
広場恐怖症の診断方法

2025年8月現在、広場恐怖症の診断には、先述の『DSM-5』と、WHOが作成している病気の統計分類である『ICD-11』が用いられています。
この2つを統合すると、以下の条件に当てはまると「広場恐怖症だ」と診断されます。
広場恐怖症の診断基準(DSM-5とICD-11の統合)
◆恐怖や不安を感じる対象(以下のうち、2つ以上の状況)
・ バスや電車などの公共交通機関
・ 駐車場や市場などの広い場所
・ 映画館やショッピングモールなどの、人に囲まれる場所
・ 行列や人混みの中
・ 家の外に一人でいること
◆恐怖や不安の内容(特定条件状況下で、以下のうち、いずれかあるいは両方がみられる)
・「逃げ出すことが難しい」「助けてもらえない」「発作が起きたときに対応できない」といったことに大きな恐怖・不安を抱く
・ めまいや失神、動悸などの自分でコントロールできない症状を他者に見られることを強く恐れる
◆回避行動について(恐怖を抱く状況や、それによる症状を恐れることで、以下のようなことが起きる)
・ 特定の状況を積極的に回避する
・ 信頼できる相手と一緒でなければ、耐えられない状態になる
・ 極度の恐怖や不安を感じながら耐える
◆恐怖や不安の程度
その状況における実際の危険度や、社会文化的背景と比較すると、著しく過剰に恐れている
◆生活への影響
日常生活や社会生活、仕事・学業などに著しく支障をきたしている。あるいは、強い苦痛を感じながら耐えている
◆症状について
ほかの精神疾患や身体疾患では説明がつかない
上記に当てはまる状態が6か月以上続く場合は、広場恐怖症と考えられるでしょう。
ご不安な場合は、専門家の見解をご確認ください。
広場恐怖症の治療法

広場恐怖症を改善する方法には、薬物療法と精神療法の2種類があります。
医療機関では、薬物療法を用いて不安や恐怖を軽減しつつ、精神療法で不安や恐怖に慣れていくという併用が一般的です。
薬物療法
広場恐怖症の薬物療法では、主に以下の薬が用いられます。
広場恐怖症の治療で使われる薬
◆SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
・不安を緩和する薬
・うつ病の治療にも用いられるが、うつ病の場合よりも少ない量から服用を始める
・服用開始直後は眠気やめまいなどの副作用がみられることがあるが、飲みつづけると改善することが多い
◆抗不安薬(※ベンゾジアゼピン系が中心)
・強い恐怖や不安を緩和する薬
・恐怖に直面したときに、心を落ち着かせるために服用する
上記の薬は、長期的に使用すると依存してしまうリスクもあるため、主治医と相談しながら適切にコントロールしていくことが望ましいです。
精神療法
広場恐怖症に対する精神療法では、認知行動療法や森田療法などが用いられます。
認知行動療法のなかでも、広場恐怖症へのアプローチとして特に知られているのは、暴露反応妨害法です。
暴露反応妨害法では、不安を感じる状況にあえて直面したうえで「恐れていたようなことは起きない」ことを経験し、恐怖を緩和していくことを目指します。
また森田療法は、不安や症状をなくそうとすることをやめて、自身の「あるがまま」をそのままにすることを目指す療法です。
不安・恐怖そのものや、不安を感じる特定の対象・状況をどうにかしようとするのではなく、「自分自身の生活を立て直す」という広い視野で捉えます。
これを続けることにより、不安や恐怖にとらわれていた自身のあり方が徐々に変化していくのです。
精神療法は、ご自身の考え方や症状の原因などによりそれぞれ相性が異なるので、自分に合うものを選びましょう。
広場恐怖症の治療期間

広場恐怖症の改善に要する期間は、人によって大きく異なっており、数か月~1年程度で終える場合もあれば、長期間にわたって向き合う必要がある場合もあります。
個々人の症状や程度などにより必要な期間は違うため、一概に言えないのです。
そのため、「一定の時間がかかることもある」と理解したうえで治療を継続することが大切です。
「早く何とかしないといけない」と焦るのではなく、ご自身に必要な時間だと捉えて向き合っていきましょう。
広場恐怖症は、焦らず向き合えば改善できる

今回は、広場恐怖症についてお伝えしました。
主に“逃げられない”ことが原因で、特定の場所や状況に大きな恐怖を抱いてしまう広場恐怖症は、適切な対処方法をとれば改善できます。
薬物療法のほか、認知行動療法や森田療法など、さまざまなアプローチがあり、適した方法やそれに要する期間は人によって異なります。
今は大きな不安の中にいらっしゃるかもしれませんが、まずは「改善できるものだ」ということを意識してみましょう。
森田療法にご興味のある方は、自助グループ・NPO法人である生活の発見会までご相談ください。
広場恐怖症をはじめとする神経症を乗り越えた方々とともに、森田療法について学べる集談会を実施しております。
