軽度のパニック障害では、症状にどのような特徴がみられる?治った体験談をご紹介!

日常生活で「突然強い不安感を覚える」「息が苦しくなる」といった経験をしたことはありませんか?
こうした症状は“パニック障害”が関係している可能性もあり、放置すると生活に支障をきたしかねません。
今回は軽度のパニック障害でみられる症状を、発症する原因や対処法とともに紹介します。
NPO法人生活の発見会は、医療機関でないため、薬を使わず根本的に神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)に対処する「森田療法」が学習できる自助組織です。
全国120の森田療法協力医と連携し、神経症でお悩みの方を支援しています。
以下動画では、森田療法について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
NPO法人生活の発見会では、「森田療法」を学び、神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)を乗り越えた人達が中心となり「森田療法」を学び合える集談会を開催しています。
集談会では、同じ悩みを持った人達の話が聞けるため”自分の苦しみを共有”することができます。また、神経症を克服した人の話も聞けるので、症状克服への知恵と力がもらえます。
集談会に参加することで、神経症克服の第一歩となるでしょう。
予約なく参加も可能ですので、ぜひお近くの集談会に「お試し参加」してみてください。
パニック障害とは
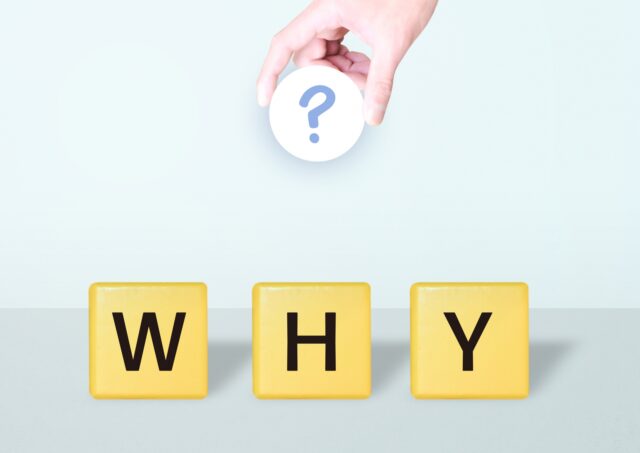
“激しい不安に襲われる”“息苦しい”“ふらふらする”など、心身に影響を与えるパニック発作が繰り返し起こるのが、パニック障害です。
発作は数十分程度で自然に収まることが多いものの、予期せぬタイミングで起こるため生活に不都合が生じるおそれもあります。
発作の再発に不安を感じ、次第に人混みや外出を避けるようになるケースも珍しくありません。
パニック障害を発症後、適切な治療を受けずそのままにしておくと、症状が悪化するほか、うつ病をはじめさまざまな症状を併発するリスクが高まります。
そのため、生活のなかで「理由もなく不安になる」「急にめまいが起こる」などの症状が頻繁に起こるようになった場合は、自助グループや医療機関に相談することが大切です。
自助組織「生活の発見会」では、森田療法を学ぶことでパニック障害の克服を支援しています。
和田秀樹先生のYouTubeチャンネルで「生活の発見会」が取り上げられました。
パニック障害の具体的な症状

パニック障害を正しく理解するためには、どのような症状がみられるのかを知ることが大切です。
具体的な症状としては、以下が挙げられます。
【パニック障害の症状・パニック発作の例】
- 胸の痛み・不快感
- 動悸・頻脈
- めまい
- 息切れ・息苦しさ
- 手足の震え
- 吐き気
- ほてり・悪寒
- 発汗
- しびれ
- 死への恐怖
上記を見てみると、心身の両面で症状が現れることがおわかりいただけるのではないでしょうか。
パニック障害が軽度の場合と重度の場合では、現れる症状に違いはあまりみられませんが、その頻度や強さが異なります。
以下で、それぞれの特徴を見ていきましょう。
軽度の場合
パニック障害が軽度の場合は、パニック発作が起こる頻度が低く、発生する場面が限定される傾向にあります。
「月に数回だけ息苦しさを感じる」「電車に乗るときだけ強い不安を感じる」など、症状の程度は比較的軽いのが特徴です。
症状の軽さゆえに放置してしまうかもしれませんが、パニック発作が起こるタイミングは予測できないため、生活に影響が出る可能性もあります。
軽微な症状であっても、次第に重症化するおそれもあるので、違和感を覚えたら早めに治療を開始することが大切です。
重度の場合
「急に不安を感じることもあるけれど、問題ないだろう」と、違和感があるにもかかわらず放置するのは避けたいところです。
症状が悪化し、軽度の場合と比べて発作回数が増えたり、強い発作が現れたりと日常生活に支障をきたす可能性が高まります。
そして「また発作が起きてしまうのではないか」という“予期不安”が強くなるのも、パニック障害が進行した場合の特徴です。
未来に対する過剰な不安や恐怖から、発作が起こりそうな状況を避けるようになります。
たとえば「電車に乗らないようにする」「人混みを避ける」など、行動範囲が極端に狭まるため通勤・通学が困難になるほか、孤立感も深まるでしょう。
こうした状況によって精神的な負担が大きくなると、うつ病をはじめとする症状を併発することもあります。
重度のパニック障害から抜け出すのは容易ではありませんが、適切な治療を受ければ、不安や恐怖に向き合いながら、緩和を目指せます。
予期不安について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
「予期不安とは?症状や克服する方法を解説」
パニック障害を発症する原因
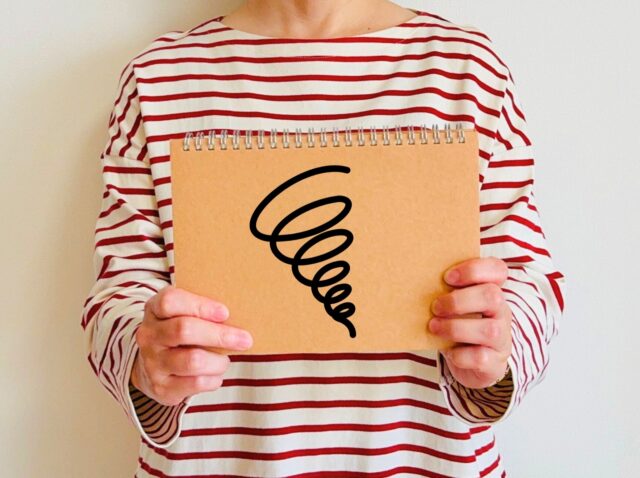
続いて、パニック障害を発症する原因について見ていきます。
現在、パニック障害の原因は解明されていませんが、“ストレス・遺伝・脳のはたらき”の3つが関係していると考えられています。
以下で、一つずつ確認していきましょう。
【パニック障害の原因】
- 原因①過度なストレス
- 原因②遺伝
- 原因③脳のはたらきの異常
原因①過度なストレス
パニック障害の発症には、ストレスが関係していると考えられています。
強いストレスを抱えた状態が続くと、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れて、不安や恐怖に敏感に反応するようになります。
たとえ弱いストレスであっても、蓄積すれば症状が深刻になるでしょう。
また、過去に大きなストレスを感じた経験がトラウマとなり、パニック障害につながるおそれもあります。
たとえば電車でのネガティブな記憶がある場合、同じような状況に直面した際に発作が起こるケースも珍しくありません。
パニック障害に悩まないためにも、リラックスする時間を確保したり、専門家の力を借りつつ過去と向き合ったりと、ご自身に合う方法でストレスを緩和させるのが大切です。
原因②遺伝
親がパニック障害を発症している場合、その子どもも発症するおそれがあります。
すべての方に該当するわけではありませんが、親がパニック障害を発症していないケースと比べると、遺伝的な要因によって発症のリスクが高まると考えられています。
ただしパニック障害の発症に関与する遺伝子は、現時点では特定されていません。
発症にはさまざまな要因が絡み合うといわれており、遺伝だけが原因で起こるわけではないとご理解ください。
原因③脳のはたらきの異常
脳内の器官のなかでも、不安や恐怖に大きく関わっている“扁桃体(へんとうたい)”が過剰にはたらくことも、パニック障害を発症する原因の一つといわれています。
扁桃体とは脳の深層にある器官で、外部からの情報が安全かどうかを判断し、それに基づいて不安や恐怖、喜び、怒りなどの感情を引き起こすはたらきがあります。
外部から危険を察知した際に活性化し、ネガティブな感情を発生させて身を守るための行動を促すのが役目です。
記憶を司る“海馬”とよばれる器官とも連携し、危険だと判断した情報の記憶を形成する役割も果たしています。
しかし、ストレスが慢性化すると脳内の神経伝達物質のバランスが乱れ、扁桃体が過剰に反応するようになります。
その結果、危険ではない情報や小さな刺激に対しても危険と判断し、強い不安や恐怖を引き起こしてしまうのです。
こうした扁桃体の過剰なはたらきがパニック発作の引き金となり、ひいてはパニック障害が発症すると考えられています。
パニック障害を発症する可能性が高い方の特徴

パニック障害は決して珍しいものではなく、誰にでも起こりうる症状です。
なかでも、以下のような特徴がみられる方は発症しやすいとされています。
【パニック障害を発症しやすい方の特徴】
- 真面目で完璧主義の方
- 自律神経が乱れている方
- 不安や恐怖を感じやすい方
- うつ病を発症したことのある方
パニック発作に悩まされる日々が続くと、以前よりも毎日を楽しめなくなることがあるため、こうした傾向のある方は早めの対処を心がけることが重要です。
それでは、以下で特徴の詳細を見ていきましょう。
真面目で完璧主義の方
真面目で完璧主義な方は、パニック障害に悩みやすいとされています。
勉強や仕事、家事など何事も正確、かつ完璧に行おうとするあまり、自分自身で大きな負担をかけてしまいます。
責任感が強く、高い目標を掲げる傾向にあるため、無理をしすぎることも少なくありません。
自分自身を追い込むほど頑張ってしまうからこそストレスを蓄積しやすく、その結果パニック障害を引き起こすおそれがあるのです。
自律神経が乱れている方
「長時間労働が続いている」「睡眠時間を確保できていない」など、忙しい日々を過ごすなかでは正しい生活リズムを維持できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不規則な生活が続くと自律神経が乱れ、パニック障害を発症する可能性が高まるとされています。
自律神経は“副交感神経”と“交感神経”の2つに分かれており、状況に応じて相反するはたらきをすることでバランスを保っています。
たとえば、睡眠中は身体を休ませる副交感神経が活発にはたらき、身体を活発化させる交感神経は活動を抑えるといった具合です。
しかし生活リズムが乱れている場合、それぞれが本来の役割を果たせません。
休養が十分に取れていないと、夜間でも交感神経が優位なままとなり、心身がリラックスできない状態になります。
自律神経の乱れは、心身を疲弊させてストレスに過度に反応する状態をつくります。
生活リズムが整っていない方は、こうしたリスクが上がるため、パニック障害を発症しやすいと考えられているわけです。
不安や恐怖を感じやすい方
パニック障害に悩む方には、生まれ持った気質にも特徴がみられます。
もともとの気質が「内向的で慎重である」「共感力が高い」といった傾向にある方は、さまざまな場面で不安や恐怖を抱えることがあるかもしれません。
またこうした気質は、過去の経験によって形成されるとも考えられています。
たとえば、幼少期に「失敗すると怒られる」「困っていても助けてもらえない」といった経験をした場合、そこで感じた不安や恐怖は心に残りつづけてしまいます。
それと同時に物事をネガティブに捉える考え方も染みつくため、不安や恐怖を感じやすくなるのです。
このように些細な出来事に対しても過度に不安を感じる方は、パニック障害になる傾向が大きいといえます。
うつ病を発症したことのある方
パニック障害とうつ病の関係は深く、どちらか一方を発症すると、もう一方の症状も引き起こされるリスクがあります。
そのため現在、うつ病と向き合っている方やうつ病の既往歴がある方は、パニック障害を発症する可能性が高いと考えられています。
これらを併発した場合、それぞれの症状が影響し合い、重症化しかねません。
予期不安が強くなったり、数週間以上、気分が落ち込んだ状態が続いたりと、心に疲労が蓄積してしまうことがあります。
パニック障害とうつ病は、どちらも発症している期間が長いほど、同時に起こる可能性が高いとされています。
関連記事:うつ病とパニック障害は併発する?関係性や治療方法も解説
パニック障害の早期発見につながるチェック項目

パニック障害の症状が軽い場合はつい見過ごしてしまいがちですが、放置すると健康的な生活を送るのが難しくなるため、初期段階で治療を開始することがポイントです。
適切なタイミングで治療を開始するためにも、以下を参考にパニック障害を疑う症状が現れていないかどうかを確かめましょう。
【パニック障害のチェック項目】
- 胸部に不快感がある
- 胸の痛みを感じる
- 動悸や心拍数の急増を感じる
- ふらつきや頭が軽くなる感じがある
- 息切れ感や息苦しさがある
- 手足が震えることがある
- 吐き気がある
- 腹部に不快感がある
- 身体が熱く感じたり、冷たく感じたりする
- 発汗や脂汗がみられる
- 感覚がマヒしている
- 「死ぬのではないか」と恐怖を感じる
- 「不安をコントロールできない」「気が狂う」と感じる
上記の項目のうち4つ以上に当てはまるものがある場合は、パニック障害の可能性があるため、医療機関の受診をおすすめします。
なお、チェックリストはパニック障害を診断するものではありません。
あくまでも医療機関を受診するきっかけを提供するものですので、診断には医師による問診や検査が必要です。
軽度のパニック障害を発症した際の対処法

パニック発作が起こると恐怖感や焦燥感に駆られますが、時間とともに自然に収まります。
そこで、対処法として、苦しくても恐怖感や焦燥感をそのまま感じながら必要な行動をしていればいつの間にか苦しい感情は流れることを体験から理解することが大切です。
症状が起きても必要な行動ができたという実績を自信にしてパニック障害を乗り越えていきましょう。
深呼吸をして心を落ち着かせる
パニック発作が起きている際は、自律神経の乱れから呼吸が速く、浅くなりがちです。
発作を和らげ、気持ちを落ち着かせるためにも、まずは呼吸を整えることが大切です。
3秒かけて口から息を吐き出したあと、同じように3秒数えながら次は鼻から息を吸い込みます。
これを5~10分程度行うことで、次第に不安感や恐怖感が薄れていくと考えられています。
呼吸が浅くなると「このまま息ができなくなったらどうしよう!」と不安になるかもしれませんが、そのような心配は必要ありません。
深呼吸をしながら「窒息の心配はないよ」と、心の中でご自身に声をかけてあげると、安心感も高まるでしょう。
意識的に別のことを考える
突然パニック発作が起こると、頭の中が「どうしよう」という不安や恐怖で支配され、より症状が悪化してしまう場合があります。
そうならないためにも、発作が起きたら意識の焦点を別のものに移しましょう。
「今日は晴れていて空が青いな」「今夜はアロマの香りを楽しみながらお風呂に入ろう」など、パニック発作以外のことに意識を集中させてみてください。
パニック障害を発症した際の治療法

パニック障害の症状を和らげるには、ご自身で対処するほか、自助グループや医療機関の力を借りるのも重要です。
パニック障害へのアプローチには“精神療法”と“薬物療法”があり、これらを組み合わせて症状の緩和を目指すこともあります。
それでは、それぞれの治療法について以下で見ていきましょう。
精神療法
パニック障害の精神療法では、主に“認知行動療法”や“森田療法”が用いられます。
認知行動療法とは、ご自身の考え方と、それに伴う行動にはたらきかける治療法のことです。
カウンセラーや医師との対話を通じて自分自身を客観的に捉え、パニック障害と上手に付き合うことを目指しています。
偏った考え方を修正したり、喜びを感じる活動を増やしたりと、不安や恐怖に対応する方法を身につけていきます。
一方、森田療法は不安や恐怖を、人間が持つ自然な感情として“あるがまま”に受け入れることを目指す治療法です。
たとえば、外出する前に「具合が悪くなったらどうしよう」と不安になった場合、この感情は「いつも健康でいたいという気持ちの現れなのだ」と受け入れる心を育てます。
このように不安や恐怖を排除せずに受け入れる心は、頭で理解するだけではなく、日常生活を通じて身につけていくのがポイントです。
パニック障害の症状にとらわれすぎず、生活そのものに目を向ける点が、森田療法の特徴です。
森田療法は自助組織「生活の発見会」で学ぶことができます。
薬物療法
薬物療法では、主にパニック発作を緩和する“抗不安薬(ベンゾジアゼピン系)”と予期不安の軽減が期待できる“抗うつ薬(SSRI)”の2種類の薬が用いられます。
パニック障害の緩和を目指すうえでは、これらの薬を服用すると同時に、精神療法にも取り組むことが重要だとされています。
薬を服用する際は、医師の指示に必ず従ってください。
自己判断で服用を中止する、もしくは量を増減してしまうと、症状の緩和が見込めないため注意が必要です。
パニック障害(パニック症)が治ったという方の体験談
日常生活に支障を来すほどの人に対する不安や緊張を感じるパニック障害は、治せない症状ではありません。
実際に森田療法でパニック障害(パニック症)が治ったという方の体験談をご紹介します。
【体験談】
|
パニック障害(パニック症)に悩んでいたこちらの体験者は、森田療法の自助グループでありのままの自分を受け入れられた安心感から立ち直る希望が持てたという事です。
軽度のパニック障害では症状が比較的軽い。放置せず、早めに対処しよう
パニック障害では、強い不安や胸の痛み、動悸、めまいなどのパニック発作が繰り返し起こります。
発作は予期せぬタイミングで起こるため、日常生活に影響を与える可能性があります。
軽度のパニック障害の場合は、比較的症状が軽いので「問題ない」と見過ごされがちですが、放置すると症状が悪化することも少なくありません。
そのため、少しでも心身に違和感を覚えた際は自助グループや医療機関の力を借りながら、早めに対処するのが大切です。
今回お伝えした“森田療法”にご興味のある方は、生活の発見会にぜひご相談ください。
生活の発見会では、森田療法を学ぶ機会や同じ悩みを持つ方々との交流の場を提供しております。
まずはお近くで開催している集談会へ、お気軽にご参加ください。
