パニック障害に似た病気とは?症状に応じた診療科も紹介

パニック障害は不安や恐怖といった精神的な症状だけでなく、動悸や息苦しさなどの身体的な症状を伴います。
このような症状は、パニック障害以外の病気でもみられることがあります。
本記事では、パニック障害に似た症状を引き起こす病気を解説するので、思い当たる症状がある方は、治療の方向性を決める一つの判断材料としてお役立てください。
NPO法人生活の発見会は、医療機関でないため、薬を使わず根本的に神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)に対処する「森田療法」が学習できる自助組織です。
全国120の森田療法協力医と連携し、神経症でお悩みの方を支援しています。
以下動画では、森田療法について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
NPO法人生活の発見会では、「森田療法」を学び、神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)を乗り越えた人達が中心となり「森田療法」を学び合える集談会を開催しています。
集談会では、同じ悩みを持った人達の話が聞けるため”自分の苦しみを共有”することができます。また、神経症を克服した人の話も聞けるので、症状克服への知恵と力がもらえます。
集談会に参加することで、神経症克服の第一歩となるでしょう。
予約なく参加も可能ですので、ぜひお近くの集談会に「お試し参加」してみてください。
パニック障害の症状とは?

まず、パニック障害でみられる主な症状を整理しましょう。
【パニック障害の症状】
- 突然の激しい動悸
- 強い胸の痛み
- 息苦しさや窒息感
- めまいやふらつき
- 発汗
- 手足のしびれや震え
- 強い不安感
- 死への恐怖感
- 非現実感
これらの症状が10分程度でピークに達し、数分から数十分間続く状態を“パニック発作”といいます。
パニック発作は前触れがなく、いつどこで起こるかがわからないため、日常生活に支障をきたす場合も少なくありません。
たとえば、人混みや電車を避けるといった行動によって、学校や仕事に遅刻するケースです。
なお、同様の症状はほかの病気でも現れることがあります。
関連記事:パニック障害(パニック症)とは?治った体験談をご紹介!症状や原因、治療法についても解説!
和田秀樹先生のYouTubeチャンネルで「生活の発見会」が取り上げられました。
パニック障害を引き起こす原因
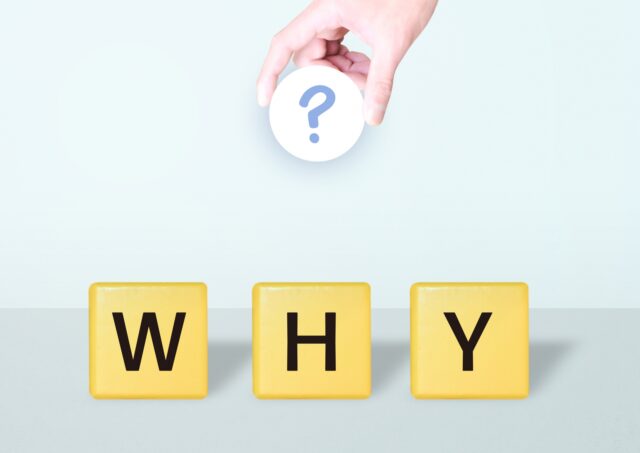
パニック障害を引き起こす原因は、まだ完全には解明されていません。
しかし、以下のようなさまざまな要因が重なり合って発症すると考えられています。
【パニック障害の発症に関わるとされる要因】
◆心理的要因
- 強いストレス
- 過去のトラウマ体験
- 性格傾向(完璧主義、心配性など)
◆心理的要因
- 脳内の神経伝達物質のバランスの乱れ
- 自律神経の乱れ
- ホルモンバランスの変化
◆遺伝的要因
- 家族に不安障害やうつ病などの既往歴がある
このようにパニック障害は、性格傾向や家族歴によっても発症する可能性があります。
また、睡眠不足やアルコールの過剰摂取といった生活習慣の乱れも、パニック障害を引き起こす原因の一つです。
生活習慣が乱れると、感情をコントロールする脳内の神経伝達物質のバランスが崩れるため、必要以上に不安や恐怖を感じやすくなります。
パニック障害に似た症状が現れる病気

動悸や息苦しさ、また強い不安感などは、パニック障害以外の病気でもみられる症状です。
以下では、パニック障害と似た症状が現れる代表的な病気を取り上げ、それぞれの特徴を説明します。
【パニック障害に似た症状が現れる病気】
- 精神疾患
- 心臓疾患
- 甲状腺機能亢進症
- 呼吸器疾患
- 機能性低血糖症
- 更年期障害
精神疾患
以下のような精神疾患は、パニック障害との区別が難しいことがあります。
【パニック障害と似た症状がみられる疾患】
◆疾患
- うつ病
- 不安障害
- PTSD
- 強迫障害
◆主な症状
- 強い気分の落ち込み、憂うつ感
- トラウマ体験によるフラッシュバックや悪夢
- 過剰な不安や恐怖
- 動悸や発汗
◆発症に関係する要因
- 強いストレス
- 脳内の神経伝達物質のバランスの乱れ
- 事故や災害、暴力などの心的外傷体験
- 性格傾向
- 遺伝的要因
これらの疾患ではパニック障害と似た症状が現れるのが特徴です。
パニック障害と併発する可能性もあるため、誤解されやすい疾患であるといえます。
症状を引き起こすとされる要因もパニック障害と酷似しており、判断が難しいケースも少なくありません。
心臓疾患
動悸や胸痛などの症状が起こる心臓疾患も、パニック障害と間違えやすい病気の一つです。
具体的な疾患や症状は、以下をご確認ください。
【パニック障害と似た症状がみられる心臓疾患】
◆疾患
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 不整脈
◆主な症状
- 動悸
- 胸の痛みや圧迫感
- 息苦しさ
- めまい、ふらつき
- 冷や汗
◆発症に関係する要因
- 高血圧
- 動脈硬化
- 肥満
- 喫煙
- アルコールやカフェインの過剰摂取
症状はパニック障害と類似するものの、原因が特定しやすいため、判別できる可能性は高いといえます。
心臓疾患は生活習慣病が原因で発症するケースが多く、喫煙や飲酒の習慣がある方、また太り気味の方によくみられます。
甲状腺機能亢進症
甲状腺の疾患である“甲状腺機能亢進症”においても、パニック障害と似た症状が現れることがあります。
甲状腺機能亢進症の主な特徴は、以下の通りです。
【甲状腺機能亢進症の特徴】
◆主な症状
- 動悸
- 発汗
- 手の震え
- 体重減少
◆発症に関係する要因
- 甲状腺ホルモンの過剰分泌
- 甲状腺の炎症
- 薬剤による影響
この疾患の原因は現時点では解明されていないものの、自己免疫疾患による甲状腺ホルモンの過剰分泌が大きく関係していると考えられています。
甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると、眼球の突出や首元の腫れといった特有の症状が現れるので、見た目の違いでパニック障害と判別できる可能性があります。
また、甲状腺の疾患では、食事をしっかりと摂っているにもかかわらず体重の減少がみられるのが特徴です。
呼吸器疾患
胸の圧迫感や息苦しさといった症状を引き起こす以下のような呼吸器疾患も、パニック障害と間違えやすい病気として挙げられます。
【パニック障害と似た症状がみられる呼吸器疾患】
◆疾患
- 過換気症候群
- 気管支喘息
◆主な症状
- 胸痛
- 息苦しさ、窒息感
- 不安感
- 集中力の低下
- 喘鳴(ぜんめい)
◆原因
- ストレス
- 感情の高ぶり
- ウイルス感染
- アレルギー症状
過換気症候群は急性と慢性に分けられ、急性の場合は窒息感と強い胸痛を伴うので、パニック発作と区別がつきにくいのが特徴です。
一方、慢性の場合は呼吸の症状は軽度であることが多く、不安感が生じたり集中力が低下したりと、精神的な症状が強く現れます。
また気管支喘息も、喘息発作により窒息状態になるケースがあるため、パニック障害と誤解されやすい疾患の一つです。
気管支喘息は、ウイルスやアレルギーなどなんらかの要因によって気道に炎症が起き、空気の通り道が狭くなることで発症します。
気道が狭くなると、呼吸時に「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった喘鳴(ぜんめい)が起こるのが特徴です。
これらの疾患は適切な治療を受ければ症状の改善が期待できますが、パニック障害と間違えてしまうと診断が遅れる可能性もあります。
医療機関を受診する際は、あらゆる疾患の可能性を視野に入れ、医師に症状を伝えることが大切です。
機能性低血糖症
血糖値が急激に下がることで引き起こされる“機能性低血糖症”も、パニック障害と似た症状が現れる疾患です。
主な特徴は、以下をご覧ください。
【機能性低血糖症の特徴】
◆疾患
- 動悸
- めまい
- 手足の冷え
- 不安感
- 集中力の低下
◆原因
- 糖質が多い食品の過剰摂取
- 過度な糖質制限
- 栄養バランスの偏り
低血糖症と聞くと、糖尿病に罹患(りかん)している人が発症すると思われるかもしれませんが、実際には関係がありません。
機能性低血糖症は、糖質が多い食品の過剰摂取によって急上昇した血糖値を下げるために、インスリンが大量に分泌されることで引き起こされると考えられています。
不安感の増幅や集中力の低下といった精神的な症状も伴うため、パニック障害と誤診されるケースもあります。
更年期障害
更年期障害も、パニック障害と混同しやすい疾患に含まれます。
この疾患の主な症状や原因を、以下にまとめました。
【更年期障害の特徴】
◆主な症状
- 動悸
- 息切れ
- 発汗、ほてり(ホットフラッシュ)
- 不安感
◆原因
- 加齢による女性ホルモンの急激な減少
- ホルモンバランスの乱れ
更年期障害は主に40~50代の女性に多くみられ、女性ホルモンの急激な減少によって動悸や息切れ、また発汗といったパニック障害と似た症状が現れるのが特徴です。
自律神経が不安定な状態が続き、イライラや気分の落ち込みなどで感情のコントロールが難しくなります。
特に、更年期障害の代表的な症状であるホットフラッシュは、動悸や発汗が突然現れるので、パニック発作と混同されることがあります。
パニック障害に似た症状が現れたらどの診療科を受診する?

パニック障害以外の病気が疑われる場合には、症状に応じて最適な診療科を受診することが大切です。
ご自身にどのような症状が強く出ているのかを把握したうえで、以下を参考に、受診すべき診療科を絞り込みましょう。
【考えられる疾患と受診すべき診療科】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上記の内容は、あくまでも代表的な症状をベースにしています。
症状によってはより専門的な治療が必要になるケースもあるため、気になる症状がある場合には、医師に相談してください。
パニック障害の治療方法

医療機関を受診した結果パニック障害と診断された場合には、どのような治療が行われるのでしょうか。
パニック障害には、“精神療法”と“薬物療法”の2つの治療方法があります。
それぞれの治療方法を、以下で詳しく見ていきましょう。
精神療法
精神療法は不安を軽減することを目的としており、瞑想や呼吸法にくわえて“認知行動療法”が行われるのが一般的です。
認知行動療法では、パニック発作につながる思考や行動を特定し、自分でコントロールできる状態を目指します。
発作が起きるような状況にあえて身を置き「実際に発作は起きない」と認識することで、徐々に考え方の癖がなくなり、その状況に適応できるようになります。
しかし、治療とはいえ「発作が起きる状況に向き合うのは怖い」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方には、症状を解消するのではなく自分の思考や行動を“あるがまま”に受け入れ、人間らしく生きることを目指す“森田療法”という方法がおすすめです。
森田療法では、パニック発作につながるような不安や恐怖をなくそうとはせずに、自分の自然な感情と捉え、理解を深めていきます。
症状として認識しているものを、あくまでもただの不安として考えらえる状態に戻すのです。
森田療法は、精神科や心療内科などで取り入れている場合もありますが、すべての医療機関で受けられるわけではないため、事前に確認してから受診するとよいでしょう。
また、森田療法を取り扱う自助グループでは、カウンセリングや日記療法などが受けられる場合もあります。
自助組織「生活の発見会」では、パニック障害を克服した方々と共に、森田療法を学ぶことができます。
薬物療法
パニック発作が起きる頻度が高い、あるいは日常生活に大きな支障をきたしている場合には、薬物療法が用いられます。
薬は“選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)”や“セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)”などの抗うつ薬を使用するのが一般的です。
ただし、これらの薬は効果を発揮するまでに数週間程度かかることもあるため、即効性を重視する場合は、ベンゾジアゼピン系薬剤を併用します。
薬の服用によってパニック発作が落ち着く、また頻度が減るなどの効果が期待できますが、眠気や記憶障害といった副作用が起こるケースも少なくありません。
また、服用を中止すると発作が再発する可能性が高いので、長期的な服用が必要になる場合もあります。
パニック障害に似た症状が現れる病気は数多く存在する
パニック障害に似た症状が現れる病気は、心臓疾患や甲状腺疾患、また更年期障害などさまざまです。
少しでも早く症状を改善するためには、どのような症状が強く出ているのかを把握したうえで、最適な診療科を受診することが大切です。
医療機関を受診した結果パニック障害と診断された場合は、精神療法や薬物療法による治療が行われます。
「パニック発作と向き合うのが怖い」「薬の服用は避けたい」という方は、NPO法人「生活の発見会」にご相談ください。
森田療法の理念のもと、パニック障害をはじめとする神経症の克服をサポートいたします。
まずはお気軽に「集談会」へご参加ください。
