不安症(不安障害)治った体験談をご紹介! 症状や原因、治療法についても解説!

漠然とした不安や心配が続き、精神的・身体的な不調を感じている場合は、“不安症(不安障害)”を患っている可能性があります。
深刻化すると日常生活に支障をきたすおそれがあるため、心当たりのある方はご自身の現状を正しく理解したうえで、治療に専念することが大切です。
本記事では、不安症(不安障害)の症状やセルフチェック方法、治療法について解説します。
一人で悩まず、適切に対処していくことが苦しみを取り除く第一歩です。
NPO法人生活の発見会は、医療機関でないため、薬を使わず根本的に神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)に対処する「森田療法」が学習できる自助組織です。
全国120の森田療法協力医と連携し、神経症でお悩みの方を支援しています。
以下動画では、森田療法について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
NPO法人生活の発見会では、「森田療法」を学び、神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)を乗り越えた人達が中心となり「森田療法」を学び合える集談会を開催しています。
集談会では、同じ悩みを持った人達の話が聞けるため”自分の苦しみを共有”することができます。また、神経症を克服した人の話も聞けるので、症状克服への知恵と力がもらえます。
集談会に参加することで、神経症克服の第一歩となるでしょう。
予約なく参加も可能ですので、ぜひお近くの集談会に「お試し参加」してみてください。
不安症(不安障害)とは

不安症(不安障害)とは、漠然とした不安感や心配が長期間続くことで精神的・身体的な不調が現れ、日常生活に悪影響を及ぼす精神疾患のことです。
GAD(Generalized Anxiety Disorder)ともよばれるこの疾患は、不安障害の一つとして知られています。
日常生活におけるさまざまな出来事に対して、とりとめのない不安や心配を過度に感じてしまうのが主な特徴です。
以下は、不安症(不安障害)の方が過度な不安や心配を感じやすい事柄の一例です。
【不安症(不安障害)の方が不安や心配を感じる事柄の一例】
- 仕事の失敗
- 地震や台風といった自然災害
- 近親者の急死
不安症(不安障害)を患うと上記のような不測の事態に対して、理由もなく、次から次へと過度な不安や心配が湧き上がるような症状がみられます。
こうした症状を、“浮動性不安”とよびます。
不安症(不安障害)は、この浮動性不安が慢性化することで、精神的・身体的に影響を及ぼす精神疾患なのです。
和田秀樹先生のYouTubeチャンネルで「生活の発見会」が取り上げられました。
不安症(不安障害)の症状

ここからは、不安症(不安障害)が精神面と身体面のそれぞれに対してどのような症状をもたらすのかを確認してみましょう。
精神的症状
不安症(不安障害)は、精神面に対して以下のような症状を引き起こします。
【不安症(不安障害)が精神にもたらす症状】
- いらつき
- 気分の落ち込み
- 倦怠感
- 集中力の低下
漠然とした不安感によるいらつきや、気分の落ち込みといった感情の激しい起伏が、不安症(不安障害)が精神にもたらす代表的な症状です。
感情の起伏に伴うエネルギーの消耗で精神が疲弊してしまい、倦怠感を覚えやすくなります。
また、過度な不安感に気を取られやすくなり、集中力の低下を招くこともあります。
身体的症状
身体面に現れる不安症(不安障害)の症状の一例として、以下のようなものがあります。
【不安症(不安障害)が身体にもたらす症状の一例】
- 筋肉の緊張
- 頭痛
- 動悸
- 息切れ
- 不眠
不安症(不安障害)を発症すると、過度な不安や心配で筋肉が常に緊張し、自律神経の乱れを引き起こします。
その結果、血管の収縮にも影響を与え、頭痛やめまい、動悸や息切れを誘発することもあるのです。
またこうした症状は、睡眠を妨げる原因にもなります。
不安症(不安障害)の原因
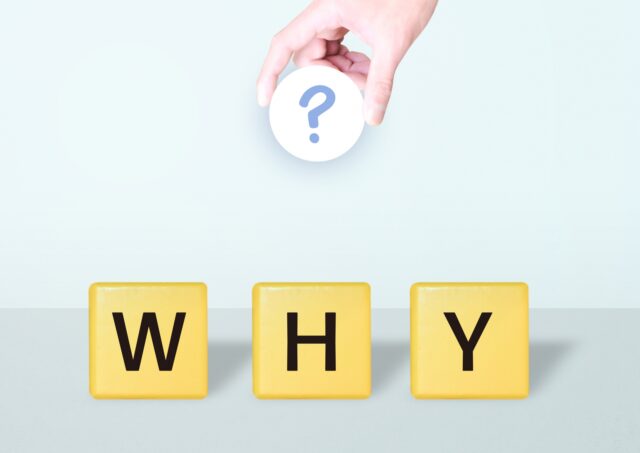
結論から述べると、不安症(不安障害)の原因は現代医学でも明らかにはなっていません。
しかし多くの場合で、以下に記した環境的要因と遺伝的要因が、複合的に作用することで発症しているのではないかと考えられています。
環境的要因
過去のトラウマや生活環境の変化が与えるストレスは、不安症(不安障害)を引き起こす要因の一つとして考えられています。
たとえば、幼少期のネグレクトや過保護といった経験や、離婚や転勤に伴う環境の変化は、精神的に大きなストレスを与えます。
こうしたストレスが、物事をネガティブに捉えやすい性格や考え方を形成し、結果的に不安症(不安障害)の一因になるというわけです。
遺伝的要因
不安症(不安障害)の発症には、親からの遺伝も深く関わっているのではないかといわれています。
不安障害に関する一部の研究では、不安症(不安障害)と診断された患者に遺伝性が認められるとする報告があるのです。
また別の研究では、遺伝子異常による脳内物質のバランスの乱れが発症に関与するのではないかとも推察されています。
いずれの研究結果も、不安症(不安障害)を持つ親の子どもが必ず発症することを裏付けるものではありません。
しかし、遺伝の影響が全くないとは言い切れず、発症に関係している可能性もあります。
不安症(不安障害)になりやすい方の特徴

不安症(不安障害)の発症には、個々人が持つ性格や気質も深く関わるといわれています。
特に発症しやすい方の特徴は、以下のようなものです。
【不安症(不安障害)になりやすい方の特徴】
- 心配性
- 完璧主義
- 内向的
- 神経質
- 衝動的
- ストレス耐性が弱い
- 自己肯定感が低い
上記のように、日常の小さな出来事でも気にしてしまう性格を持つ方は、不安症(不安障害)を発症しやすいといえます。
不安症(不安障害)のセルフチェック方法

日本不安症学会が公開しているチェックリストを使用することで、ご自身が不安症(不安障害)を発症しているのかどうかを、ある程度把握することが可能です。
直近2週間で、以下の問題に対してどれくらいの頻度で悩んでいるのかを点数化して、確認する指標となっています。
【不安症(不安障害)のチェック方法】
以下の7項目について、「全くない(0点)」「数日(1点)」「半分以上(2点)」「ほとんど毎日(3点)」の中から、当てはまる頻度を選んび、7項目の合計点を求めてください。
◆項目
①緊張感・不安感・神経過敏を感じる
②心配を止められない、コントロールできない
③さまざまなことを心配しすぎる
④くつろぐことが難しい
⑤落ち着かず、じっとしていられない
⑥イライラしやすく、怒りっぽい
⑦恐ろしいことが起こるのではないかと感じる
◆判定の目安
合計点によって、不安の程度を以下のように目安づけます。
・0~4点:軽微
・5~9点:軽度
・10~14点:中等度
・15~21点:重度
臨床現場では、上記の基準が10点以上となった場合に、不安症(不安障害)の疑いがあると見なされます。
ただし、正確な診断には医師の診察を要するため、セルフチェック後に気がかりな点がある方は、一度精神科や心療内科を受診してみるのがよいでしょう。
参照元:日本不安症学会
不安症(不安障害)の診断方法

ここからは、不安症(不安障害)の診断方法について見ていきましょう。
不安症(不安障害)の診断には、一般的に“ICD-10”と“DSM-5”という2つの診断基準が用いられています。
いずれの場合も、症状の経過や特徴を、それぞれの診断基準に基づいて総合的に分析し、判断されます。
ICD-10
ICD-10は、世界保健機構(WHO)が作成した国際的な診断基準の一つです。
少なくとも数週間程度か数か月間、ほぼ毎日、以下の症状が続いているのかどうかを確認します。
【ICD-10に基づいて確認する不安症(不安障害)の症状】
症例:心配
症状:将来の不幸に関する気がかりやいらいら感、集中困難などの症状
症例:運動性緊張
症状:筋肉の緊張に伴う頭痛や身震い、くつろぐことがでいないといった症状
症例:自律神経性過活動
症状:頭のふらつきや発汗、呼吸が荒くなるといった症状
診断にICD-10を用いた場合では、これら3つの症状を含む場合に不安症(不安障害)であると見なされます。
ただし、パニック障害や社交不安障害、強迫性障害といったほかの不安障害や、うつ病の診断基準を完全に満たす場合には、不安症(不安障害)とは診断されません。
DSM-5
アメリカ精神医学会(APA)が作成したDSM-5では、以下に示した6つの診断基準に基づいて不安症(不安障害)を発症しているのかどうかを判断します。
【DSM-5に基づいて確認する不安症(不安障害)の診断基準】
- 落ち着きがなく、緊張感や感情の高ぶりがある
- 疲れやすさを感じる
- 集中力が続かない
- いらいらする
- 筋肉が緊張する
- 入眠が困難な場合や、熟睡できないことがある
DSM-5では、日常生活のなかで抑えるのが困難な強い不安感や心配が6か月以上続いている状態で、上記の症状が3つ以上現れていることを、診断の要件としています。
また、上記の症状により苦痛が生じているのか・日常生活に支障が出ているのか・不安感や心配が身体疾患によるものでないかどうかという点も診断の基準です。
不安症(不安障害)とほかの精神疾患との違い

日常生活が困難となる精神疾患としては、うつ病やほかの不安障害(パニック障害・社交不安障害・強迫性障害)も挙げられます。
ここからは、それぞれの病気が不安症(不安障害)とどのような点で異なるのかを見ていきましょう。
うつ病との違い
不安症(不安障害)とうつ病は、主に精神的な症状が異なります。
不安症(不安障害)の場合は、強い不安感や心配が頭の中を巡りつづける精神疾患です。
これに対してうつ病は、気分が晴れず、何事に対しても意欲が湧かない状態が続く精神疾患のことです。
いずれの疾患も、日常生活で実際に起こった出来事に対するショックを引き金に発症することが多いといわれています。
発症する原因や身体に現れる症状が類似していることから混同されやすくはあるものの、まったく別の精神疾患となっている点には注意してください。
関連記事:うつ病とパニック障害は併発する?関係性や治療方法も解説
ほかの不安障害との違い
不安症(不安障害)と症状が似ている、ほかの不安障害としてパニック障害、社交不安障害、強迫性障害があります。
いずれも日常生活に支障をきたす点では共通していますが、不安の対象や症状の現れ方に明確な違いがあるのです。
以下に、それぞれの疾患の特徴をまとめました。
◆不安障害の特徴
【不安症(不安障害)】
不安を感じる状況:予測不可能なさまざまな物事や状況など
発症に伴う症状:いらいらしやすくなり、落ち着きがなくなる
【パニック障害】
不安を感じる状況:電車内やエレベーターなどの閉じた空間など
発症に伴う症状:呼吸困難や震えなどの予期せぬ発作を繰り返した経験から、同じ状況を避けようとする
【社交不安障害】
不安を感じる状況:人前や初対面の人との会話が必要となる場など
発症に伴う症状:赤面や発汗、震えが生じるため、人前に出ることを避けようとする
【強迫性障害】
不安を感じる状況:手の汚れや戸締りなど
発症に伴う症状:手洗いや、戸締りの確認を何度も行う
上記の通り不安症(不安障害)は、特定の状況下に限定されるこれらの不安障害とは異なり、さまざまな物事や出来事に対して不安や心配を抱く精神疾患なのです。
不安症(不安障害)と併発する可能性がある精神疾患

不安症(不安障害)は、以下の精神疾患を併発する可能性が高いことでも知られています。
ここからは、それぞれの関連性を詳しく見ていきましょう。
【不安症(不安障害)と併発する可能性がある精神疾患】
- うつ病
- ほかの不安障害
- アルコール依存症
うつ病
うつ病は、極度の不安が発症の引き金になるという点で不安症(不安障害)と共通しているため、併発しやすいといわれています。
不安症(不安障害)の症状がうつ病の原因となる場合もあれば、逆にうつ病の治療中に不安症(不安障害)の症状が出てくる場合もあります。
薬物治療を行う際には、いずれの精神疾患でもセロトニンのはたらきを促す薬が有効であるとされていることからも、関連性が高く、併発しやすいといえるでしょう。
ほかの不安障害
不安症(不安障害)は、特定の状況に対して不安を抱くパニック障害や社交不安障害、強迫性障害などの、ほかの不安障害と併発することもあります。
特にパニック障害の方が抱える発作への予期不安は、不安症(不安障害)が抱える不安と類似するため併発することが多いといわれています。
関連記事:予期不安とは?症状や克服する方法を解説
アルコール依存症
アルコール依存症も、不安症(不安障害)と併発する可能性がある精神疾患です。
これは、アルコールが不安症(不安障害)で生じる強い不安感から逃避する手段になりやすいためです。
万が一、不安症(不安障害)の疑いがある場合に過度な飲酒をすれば、症状を助長するだけではなく、アルコール依存症の併発にもつながりかねません。
不安症(不安障害)を予防・改善するために心がけたいこと

不安症(不安障害)を予防・改善するためには、以下の5つのポイントを心がけて生活することが重要です。
なお、これらは不安症(不安障害)の根本的な治療法とはならないため、診断された方は、医師の指示に基づいて治療に専念してください。
【不安症(不安障害)を予防・改善するために心がけたいこと】
- 生活習慣を整える
- リラックスできる方法を身につける
- カフェインやアルコールを摂取し過ぎない
- 働き方を変える
- 休養期間を設ける
生活習慣を整える
心の健康を維持するためには、規則正しい生活を心がけることが重要です。
不規則な生活習慣は、不安症(不安障害)の要因の一つにもなりえる自律神経の乱れを引き起こします。
生活リズムを整えれば、自律神経が安定しやすくなるので、不安症(不安障害)にみられる症状の改善に期待できるのです。
あわせて適度な運動を行えば、“幸せホルモン”とよばれるセロトニンの分泌が促進されるので、心をより落ち着かせることができます。
リラックスできる方法を身につける
心身をリラックスさせるのも、不安症(不安障害)を予防・改善するために心がけたいことの一つです。
不安やストレスを和らげる方法がなければ、それらが積み重なって症状を悪化させる原因となります。
友人と話したり、好きな場所に出かけたりと、ご自身が心地よいと感じられる方法でリラックスすることが大切です。
カフェインやアルコールを摂取し過ぎない
不安症(不安障害)の予防や改善には、カフェインやアルコールの過度な摂取を避けることも重要です。
カフェインやアルコールを摂取し過ぎると寝つきが悪くなるため、結果的に自律神経の乱れを引き起こします。
特にアルコールは、アルコール依存症の要因にもなりえるので、できる限り控えるように心がけてください。
働き方を変える
発症の予防や、症状の改善を図るために、働き方を変えることも検討してみましょう。
なかには、職場環境のストレスが原因で不安症(不安障害)を発症するケースもあります。
症状が気になる場合は、勤務時間や勤務形態を調整することで、不安やストレスを軽減できる可能性があります。
すでに診断を受けている場合は、その旨を上司に伝えることで、働きやすい環境づくりをサポートしてくれるでしょう。
休養期間を設ける
働き方を調整しても症状の改善が見込めない場合は、休養期間を設けることも一つの手です。
「休むことはどうにか避けたい……」と思うかもしれませんが、不安感を引きずりながら仕事を続けるよりも、効果的に改善を促すことができる場合もあるのです。
有給休暇活用した長期休暇や、休職などにより、集中的に療養することが、症状のさらなる悪化防止にもつながります。
不安症(不安障害)の治療法

不安症(不安障害)の治療には、主に薬物療法と精神療法の2つが用いられています。
ここからは、それぞれの治療法を詳しく解説します。
薬物療法
不安症(不安障害)の薬物療法には、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)が使用されます。
不安を和らげる脳内の神経伝達物質であるセロトニンの再取り込みを阻害することで機能を高める薬で、うつ病の治療にも用いられています。
SSRIは、発症要因がうつ病と類似する不安症(不安障害)にも効果的であるといわれているため、治療に使われているのです。
症状の経過によっては、より即効性のある“ベンゾジアゼピン系抗不安薬”が用いられることもあります。
精神療法
精神療法には、主に“認知行動療法”と“森田療法”の2種類が用いられます。
以下では、それぞれの治療法をご紹介します。
認知行動療法
認知行動療法とは、不安を引き起こす考え方や行動を変えることで、症状を改善していく治療方法です。
「○○した場合、こうなるに違いない」「この状況から逃れなければ不幸が起こる」といった極端な思考の歪みを修正し、安心できる経験を積み重ねることが主なプロセスです。
不安症(不安障害)だけではなく、ほかの不安障害の治療にも用いられています。
森田療法
森田療法とは、不安や心配といった不安症(不安障害)に見られる症状を、排除すべきものではなく、人間の自然な感情として受け入れることで、克服していく治療法です。
精神科医の森田正馬が、1919年に創始した独自の精神療法として知られています。
薬を使わずに根本的な治療を行いたい方は、森田療法を提供する医療機関に相談してみるのも一つの手です。
森田療法を深く学びたい場合は、自助グループに参加するのもよいでしょう。
“生活の発見会”もその一つで、森田療法を経験し、不安症と向き合いつづけてきた方々との集談会(交流会・学習会)を開催しています。
ご自身と同じような悩みを持つ方々と体験を共有し合い、共感を得ることで、不安を和らげるきっかけが見つかるかもしれません。
ご興味のある方は、生活の発見会の集談会にぜひご参加ください。
不安症(不安障害)が治ったという方の体験談
「不安症(不安障害)の症状は良くならない」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうであるとは限りません。
治療に励み、実際に不安症(不安障害)の症状が緩和した方もいらっしゃいます。
以下では、そのような方々の体験談をご紹介します。
確認行為(ガスの元栓、ドアの施錠)の強迫性障害(強迫症)を森田療法で克服! S.H 女性主婦
S.Hさんは、生活の発見会が開催する集談会でMさん、そして森田療法と出会い、悩まされていた強迫性障害との付き合い方を学ばれました。
「ガス台を確認しにいきたい」という気持ちを我慢しながら家事を続ける訓練を重ね、心を縛っていた恐怖から解き放たれる感覚を体験したそうです。
森田療法を学び、日常の中で実践を続けたことで、S.Hさんは心と行動の自由を取り戻せたのです。
【詳細は以下の記事をご覧ください。】
|
すべてを完璧に!から不完全恐怖へ。強迫性障害(強迫症)から森田療法で脱出(A・Kさん・主婦)
「きれいに掃除をして、きちんと家事をこなす」この強いこだわりが、A.Kさんを苦しめた不完全恐怖を発症させるに至りました。
うまくできないと感じて同じことを何度も繰り返し、それまでそつなくこなしていた家事が思うように進まなくなったと言います。
そのようなとき新聞記事で森田療法を知り、生活の発見会への入会を決意されました。
森田療法の理論通りに進まずに悩むこともあったものの、実践を繰り返し、「できたかどうか」ではなく「次は何をやるべきか」を考える習慣が身についてきたそうです。
【詳細は以下の記事をご覧ください。】
|
地獄のような強迫性障害(強迫症)、不安症(不安障害)を森田療法で決着をつける(S・Hさん・男性・会社員)
生活の発見会の集談会や基準型学習会(生活の発見会が主催する森田療法を体系的に学習するセミナー)に参加したS.Hさんは、そこで症状との向き合い方を学んだそうです。
逃げ場のない強迫性障害を断ち切るため、ただひたすらに森田療法の教えを実践しつづけました。
ときには自分の弱さを惨めに感じたものの、次第にやらなければならないことを一つひとつこなせるようになったと言います。
現在は楽しむ心を持って、毎日を前向きに過ごせているとのことです。
【詳細は以下の記事をご覧ください。】
|
不安症(不安障害)は漠然とした不安や心配が心身を脅かす精神疾患です

今回は、不安症(不安障害)の症状やセルフチェック方法、治療法について解説しました。
不安症(不安障害)とは、「不幸が起こるかもしれない」という漠然とした不安や心配を引き起こし、心身の不調につながる精神疾患です。
深刻化すると、感情の激しい起伏や、頭痛、動悸などの症状を伴います。
予防・改善していくためには、規則正しい生活を心がけるほか、適切な治療を受けることが大切です。
生活の発見会では、不安症(不安障害)をはじめとする不安障害の当事者同士が森田療法の理論を学びながら症状を克服することを支援しています。
同じ悩みを共有したい方や、森田療法について興味がある方は、ぜひお問い合わせください。
