強迫症(強迫性障害)の治療法は?具体的な症状や改善するための対策を解説

「ある考えが浮かんで離れない」「同じ行動を何度も繰り返す」といった症状は、強迫症(強迫性障害)によるものかもしれません。
不安や恐怖を必要以上に感じるのは性格の問題だからと諦めてしまいがちですが、強迫症(強迫性障害)は適切な治療によって改善できる可能性があります。
本記事では、強迫症(強迫性障害)の症状や治療法を解説します。
負の感情から心を解放し、明るい気持ちで毎日を過ごすための参考にしてください。
NPO法人生活の発見会は、医療機関でないため、薬を使わず根本的に神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)に対処する「森田療法」が学習できる自助組織です。
全国120の森田療法協力医と連携し、神経症でお悩みの方を支援しています。
以下動画では、森田療法について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
NPO法人生活の発見会では、「森田療法」を学び、神経症(パニック・社交不安・強迫・不安症など)を乗り越えた人達が中心となり「森田療法」を学び合える集談会を開催しています。
集談会では、同じ悩みを持った人達の話が聞けるため”自分の苦しみを共有”することができます。また、神経症を克服した人の話も聞けるので、症状克服への知恵と力がもらえます。
集談会に参加することで、神経症克服の第一歩となるでしょう。
予約なく参加も可能ですので、ぜひお近くの集談会に「お試し参加」してみてください。
強迫症(強迫性障害)とは

強迫症(強迫性障害)とは、自分でも気にしなくてよいとわかっていながら、不安や恐怖を和らげるために何度も同じことを考えたり、同じ行動を繰り返したりする精神状態のことです。
たとえば、「不要な物を捨てられずに溜め込む」「ガスの元栓や電気のスイッチを必要以上に確認する」などです。
こうした行動は一時的に不安を軽減できるものの、しばらくするとまた不安感が生じ、同じ行動を繰り返すという負のスパイラルに陥ります。
特定の思考や行動にとらわれてしまうのは、脳のはたらきや神経伝達物質のバランスの乱れが関係していると考えられており、本人の性格や意思の問題ではありません。
適切な治療やサポートを受けることにより、症状の軽減や改善が期待できます。
和田秀樹先生のYouTubeチャンネルで「生活の発見会」が取り上げられました。
強迫症(強迫性障害)の原因
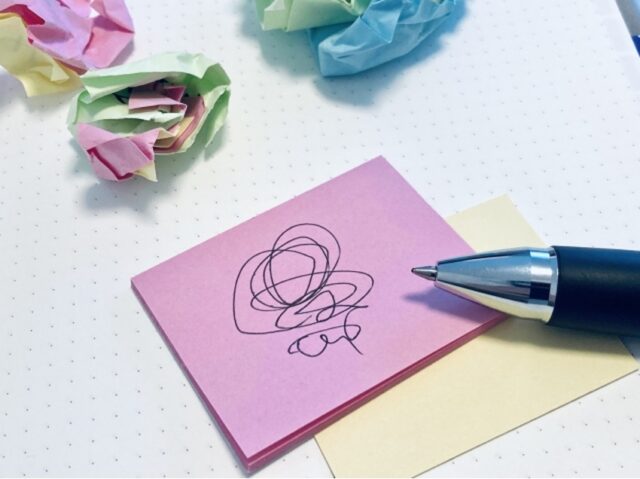
強迫症(強迫性障害)を発症する原因は、現時点では十分に解明されていません。
しかし、以下のような複数の要因が重なることで発症すると考えられます。
【強迫症(強迫性障害)の発症に関係する要因】
- ①セロトニンの不足
- ②遺伝的な要因
- ③養育者との関係
①セロトニンの不足
強迫症(強迫性障害)の発症には、セロトニンの不足が関係していると考えられています。
セロトニンは、精神を安定させるはたらきを持つ脳内の神経伝達物質の一つです。
これが不足すると、気分の落ち込みや不安感、またイライラなどが強くなり、強迫症(強迫性障害)を引き起こす可能性があります。
セロトニンは、栄養不足や睡眠不足などが原因で減少するため、規則正しい生活を心がけることが大切です。
また、適度な運動や日光浴も、セロトニンの分泌を促します。
②遺伝的な要因
家族に強迫症(強迫性障害)の人がいる場合、気質の傾向が受け継がれる可能性があり、発症リスクが高まるといわれています。
特に、幼少期や青年期に強迫症(強迫性障害)を発症するケースでは、遺伝による影響が強いとされています。
この時期は、成人期以降と比べて生活環境やストレスなどの外的要因による影響が少ない傾向にあり、生まれ持った気質が症状に強く関わっていると考えられるからです。
しかしながら、強迫症(強迫性障害)に関連する遺伝子が見つかっているわけではなく、遺伝による影響がどの程度なのかは明確になっていません。
発症には個人差があると考えられるため、家族が強迫症(強迫性障害)だからといって必ず発症するとは限らないことを、理解しておきたいところです。
③養育者との関係
遺伝的な要因にくわえて、虐待や家庭内不和などの環境的要因によっても、強迫症(強迫性障害)が引き起こされる可能性があります。
養育者による幼少期からの身体的・心理的虐待、また厳しいしつけなどは、強いストレスや不安を慢性的に与え、脳の機能に変化を及ぼすことが懸念されます。
こうした環境では、安心感や自己肯定感が育ちにくく、不安を減らすために習慣的に同じ行動を繰り返してしまうのです。
養育者との関係がきっかけで現れた強迫症(強迫性障害)状を緩和させるのは、簡単ではありません。
しかし、適切な治療を受けたり、安全な環境を確保したりすることで、症状の軽減や再発の防止につながります。
強迫症(強迫性障害)の症状

強迫症(強迫性障害)の症状は、大きく“強迫観念”と“強迫行為”の2つに分けられます。
強迫観念とは、自分でも「考えすぎだ」「行動しなくても問題ない」とわかっているにもかかわらず、ネガティブな考えが何度も思い浮かぶ症状です。
このような不安を和らげるための行動が強迫行為であり、一時的に緩和されても同じ行動を繰り返す特徴があります。
以下では、代表的な強迫観念を3つ紹介します。
それぞれに関連する強迫行為とあわせて、確認していきましょう。
【代表的な強迫観念】
- 不潔恐怖
- 加害恐怖
- 不完全恐怖
不潔恐怖
強迫観念の症状の一つに、汚染や不潔に対して恐怖を感じてしまう“不潔恐怖”があります。
たとえば、日常生活で触れる家具や家電が汚れていると感じて、「手に細菌がついて病気になるのではないか」「汚染されてしまった」などと考えてしまうのです。
このような思考により、消毒や掃除を何度も繰り返すという強迫行為につながります。
しかし、強迫行為で得られる安心感は一時的なもので、症状の根本的な改善にはなりません。
時間が経つとまた不安を感じるようになり、同じ行動を繰り返して抜け出せなくなります。
自分でも行き過ぎているとわかっているのにやめられず、日常生活や人間関係に支障をきたすことも少なくありません。
加害恐怖
「他人に危害を加えてしまうのではないか」という強い不安や恐怖を感じる“加害恐怖”も、強迫観念の症状です。
自分自身は暴力的な行動を起こしたくないと強く思っていても、「相手を傷つけてしまった」という考えが頭から離れなくなります。
このような思考により、周囲の人に何もしていないかを確認したり、新聞やテレビで報道される事件に自分が関与していないかを確認したりする強迫行為につながります。
不完全恐怖
物事や行動に対して「完璧でない」「しっくりこない」と過剰な不安や不快感を抱く場合、“不完全恐怖”という強迫観念が疑われます。
完璧主義、またはこだわりが強い性格と捉えられやすく、対称性や正確性に異常に固執する傾向があります。
具体的には、特定のかたちや位置、また順序などです。
こうした症状がみられる場合、部屋の家具や机の上にある物が決まった位置に置かれていないと気が済まず、何度も並べ直すといった強迫行為につながります。
また、入浴や着替えなどの日常的な行動でも、決まった手順を守らないと不安になり、何度もやり直すため、なかなか先に進められません。
このような症状によって一つひとつの行動に時間がかかり、学業や仕事にも悪影響を及ぼす場合があります。
強迫症(強迫性障害)になりやすい人の特徴

強迫症(強迫性障害)は、性格的・認知的・環境的な要因が組み合わさって発症することが多くみられます。
以下の表に、それぞれの傾向をまとめました。
【強迫症(強迫性障害)になりやすい人の特徴】
〇性格的特徴
- 完璧主義で、物事を納得いくまでやり遂げる
- 几帳面で、整理整頓や順序に強くこだわる
- 心配性で、失敗やリスクを過剰に想定する
〇認知的特徴
- 小さなミスや出来事も自分の責任と考えてしまう
- 不確実なことに耐えられず、何度も同じ不安を抱いてしまう
- ネガティブな思考を繰り返してしまう
〇環境的特徴
- 幼少期に厳格なしつけや虐待を受けた経験がある
- トラウマや強いストレスがある
- 家族に強迫症(強迫性障害)や不安症の人がいる
上記のように「失敗したらどうしよう……」と常に対策を考えている、またポジティブな考えがまったく浮かばない人は、強迫症(強迫性障害)を引き起こしやすいといえます。
強迫症(強迫性障害)になりやすい年齢

強迫症(強迫性障害)は、子どもから大人まで幅広い年齢で発症する可能性がありますが、特に青年期に多くみられます。
青年期とは、一般的に10代後半から20代前半の時期を指し、ホルモンバランスの変化により不安やストレスを感じやすいのが特徴です。
発症する年齢が早いほど日常生活への影響が大きくなるので、本人だけでなく周囲も感情や行動の変化に気づき、適切な治療やサポートにつなげることが重要です。
強迫症(強迫性障害)のセルフチェック方法

強迫症(強迫性障害)の症状に早く気づいて適切に対処できれば、日常生活への影響を抑えられます。
実は、日頃の自分自身の思考や行動をチェックすれば、強迫症(強迫性障害)を発症しているかどうかを確かめることが可能です。
セルフチェックの項目は、以下を参考にしてください。
【強迫症(強迫性障害)のセルフチェック項目】
- 特定の行動を繰り返してしまい、学校や職場に遅れることがよくある
- 周囲の人が時間を取らないような行動に、異常な時間や労力がかかる
- 自分の行動が過剰だとわかっていてもやめられず、ストレスを抱えている
特に、手洗いや歯磨きといった日常的な行動に時間がかかったり、周囲の人に同じことを何度も確認したりするようであれば、注意が必要です。
セルフチェック項目に当てはまるものがあり、生活に支障をきたしている場合は、医師への相談をおすすめします。
強迫症(強迫性障害)の治療法

強迫症(強迫性障害)の治療法には、主に“薬物療法”と“精神療法”があります。
それぞれ治療の目的が異なるため、これらを組み合わせることで、より高い効果が期待できます。
2つの治療法の詳細を、以下で確認していきましょう。
薬物療法
強迫症(強迫性障害)の薬物療法では、主に“選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)”という抗うつ薬を用いるのが一般的です。
この薬には、セロトニンのはたらきを高める作用があるので、強迫症(強迫性障害)の改善に役立ちます。
特に症状が強く現れているときには、医師から服用を勧められることがあります。
ただし、効果が表れるまで数週間かかる場合があり、服用初期は吐き気や頭痛といった副作用にも注意が必要です。
また、服用を急に中止すると、体内物質のバランスが崩れて心身に不快な症状が現れることがあるので、必ず医師の指示に従って服用してください。
精神療法
精神療法とは、薬を使わずに言葉の力や人とのコミュニケーションを通して、心の状態や問題となる行動の改善を目指す治療法です。強迫症(強迫性障害)の代表的な精神療法には、認知行動療法と森田療法があります。
認知行動療法にはさまざまな種類があり、そのなかでも“曝露反応妨害法(ばくろはんのうぼうがいほう)”を用いるのが基本です。
この方法では、あえて不安や恐怖を感じる状況をつくり出し、それに対する強迫行為を我慢することで、徐々に耐性を高めていきます。
行動しなくても自然に不安や恐怖を軽減する経験を重ね、強迫観念と強迫行為の負のループを断ち切ります。
一方森田療法は、不安や恐怖をなくすことを目指すのではなく、それらを“自然な感情”と受け入れ、自分が今やるべき行動に注意を向けるといった考え方の治療法です。
強迫症(強迫性障害)を改善しようと強く考えるほど、意識が集中して症状が悪化する可能性があるため、“あるがまま”を受けとめて生活を続ける姿勢を重視します。
両者はアプローチの仕方が異なるので、個人の性格や症状の特徴に応じて選択することが求められます。
強迫症(強迫性障害)が治ったという方の体験談
強迫症(強迫性障害)は、治せない症状ではありません。
実際に強迫症(強迫性障害)が治ったという方の体験談をご紹介します。
確認行為(ガスの元栓、ドアの施錠)の強迫性障害(強迫症)を森田療法で克服! S.H 女性主婦
S.Hさんは、息子たちの独立後に空の巣症候群となり、うつや強迫性障害を発症しました。
病院での治療後、生活の発見会で森田療法を学び、自身の症状と向き合います。
特に、強迫性障害を取り除くために挑戦した「ガスの元栓を気にせずに、シャツにアイロンをかける」という体験では、感情が行動と共に変化することを実感したそうです。
森田療法では“あるがまま”と“純な心”を重視しており、「不安や恐怖を否定せずに行動することで、心が自由になると学んだ」とS.Hさんは語ります。
【詳細は以下の記事をご覧ください。】
|
すべてを完璧に!から不完全恐怖へ。強迫性障害(強迫症)から森田療法で脱出(A・Kさん・主婦)
A.Kさんは結婚後、家事や育児に精を出すなか、夫からの過剰な批判により、不完全恐怖を伴う強迫性障害を発症しました。
薬の服用で不眠は改善したものの家事を何度もやり直す日々が続き、心は疲れ、荒んでいったそうです。
そのようななかで森田療法と生活の発見会に出会い、「完璧でなくても自分なりに精一杯行動する」ということを学び、実践し始めました。
最初はやり直したくなる衝動に苦しみましたが、行動を次々に進める方法を続けることで徐々に生活の能率が上がったといいます。
現在も、主婦として日常生活をこなしつつ、森田療法の学習や活動に参加しています。
【詳細は以下の記事をご覧ください。】
|
地獄のような強迫性障害(強迫症)、不安症(不安障害)を森田療法で決着をつける(S・Hさん・男性・会社員)
幼少期から漠然とした恐怖に悩まされていたS.Hさんは、勉強やスポーツで周囲より優れた成績を残すことで自己を支えてきました。
しかし大学進学後に症状が悪化し、さらにその後、東北の震災をきっかけに死への恐怖に襲われるようになったことで強迫性障害や不安障害を発症します。
S.Hさんは、森田療法と生活の発見会での学びを通じて、症状に振り回されずに丁寧に生活を送ることを実践しました。
仕事や家事を一つずつこなしながら日常生活や人との関わりを大切にすることで、症状と共存しつつ、充実した日々を送れるようになったそうです。
【詳細は以下の記事をご覧ください。】
|
強迫症(強迫性障害)と併発する可能性がある病気

強迫症(強迫性障害)は単独での発症にくわえて、ほかの精神疾患を併発する場合もあります。
以下では、強迫症(強迫性障害)と同時に発症する可能性がある精神疾患を紹介するので、詳しく見ていきましょう。
【強迫症(強迫性障害)と併発する可能性がある病気】
- 不安障害
- うつ病
- 強迫性パーソナリティー障害
不安障害
強い不安や恐怖といった強迫症(強迫性障害)の症状が長く続くと、不安障害を併発する可能性が高まります。
日常生活で感じる不安は通常、原因が解消されることで和らぎますが、不安障害はその症状が強く現れ、持続するのが特徴です。
「落ち着かない」「集中できない」「心臓がどきどきする」などの身体反応を伴うケースもあります。
不安障害には、特定の状況で発症する“パニック障害”や“社会不安障害”など複数のタイプがあり、併発すると症状が複雑化して日常生活への影響も大きくなります。
うつ病
強迫症(強迫性障害)と併発しやすい精神疾患の一つとして、うつ病も挙げられます。
強迫症(強迫性障害)の症状によって日常生活や人間関係に支障が出ると、気分が落ち込み、無力感が生じやすくなるためです。
また、両者が発症するメカニズムには、脳内の神経伝達物質の異常やストレスへの耐性など共通する部分も多く、同時に発症する可能性が高い傾向にあります。
強迫症(強迫性障害)とうつ病を併発すると、それぞれの症状が悪化する可能性があるため、両方への適切なアプローチが必要です。
関連記事:うつ病とパニック障害は併発する?関係性や治療方法も解説
強迫性パーソナリティー障害
強迫性パーソナリティー障害は、几帳面な人やこだわりが強い人によくみられる精神疾患です。
柔軟性に欠け、他人にも厳しくなりやすく、周囲の人の生活に支障をきたすことも少なくありません。
こだわりが強い点は強迫症(強迫性障害)と共通しますが、不安や恐怖を軽減するよりも自分の理想を追求し、秩序を維持することを目的に行動する点は異なります。
強迫症(強迫性障害)によるネガティブな思考や過度な行動は、薬物療法や精神療法で改善が期待できる

本記事では、強迫症(強迫性障害)の症状や治療法を解説しました。
強迫症(強迫性障害)とは、強い不安や恐怖を和らげるために、自分でも無意味だとわかっていても同じ思考や行動を繰り返してしまう精神状態のことです。
強迫症(強迫性障害)は誰にでも起こりうる状態であり、適切な診断と治療によって症状の改善が期待できます。
薬の服用に抵抗がある場合は、自分自身と向き合って強迫症(強迫性障害)の克服を目指す、認知行動療法や森田療法といった精神療法が効果的です。
「強迫症(強迫性障害)かもしれない……」とお悩みの方は、NPO法人「生活の発見会」にお問い合わせください。
本記事で紹介した森田療法について学びながら、より良い生活を目指していくという考えのもと、神経症からの克服を支援いたします。
